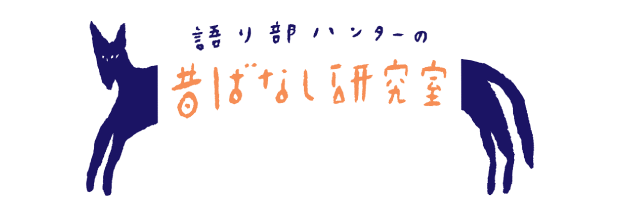vol.2大平悦子
構成・文:上條桂子
ロゴ・イラスト:山口洋佑
民話の故郷・遠野と川崎の二つの地域に住み、行き来しながら語り部として活動している大平悦子(おおだいら・えつこ)さん。
大平さんは、岩手県遠野市青笹町の生まれで、子どもの頃、祖母と母から昔の暮らしについての話をたくさん語り聞かされていたという。遠野とは、民俗学者である柳田国男の著書『遠野物語』で知られる民話の故郷のような場所だ。さぞ、楽しい話をたくさん聞いたのか、と思いきや、印象に残っているのは少々強烈な話が多いそうだ。
「昔話というよりは、“昔の暮らしの話”、生活の話が多かったんです。食べ物だとか、遊び、学校の話といったような。その中には、嫁姑の話や、世間の噂話みたいなものも入っていたんですよ。あと継子いじめの話なんかもよく聞きました。継子というのは、先妻の子どもと後妻の関係を言います。おとぎ話を聞いたというよりは、ごく普通にそうした話を聞いていました。しかも、そういう話が実際にあったんですよね。そんなわけで北国の農家の嫁は苦労するというイメージが私の中では強かったですね。だから、今、こうやって遠野に家をつくって住むなんて考えられませんでした」
継子いじめの話にどんなものがあったかというと、夜中に継子が寝ている布団の裾をペロンとめくって、こんにゃくで足の裏をトローントローンと撫でた話や、馬鍋という馬にエサをやるための大きな鍋の中に継子を突き落として殺してしまった話......。今聴くとぎょっとする内容だ。子ども時代の大平さんは、キツネやタヌキが出てくるような面白おかしい話と同様の語り口でこのような話を聞き、強烈な印象として残ったそうだ。だが、幼い頃から『遠野物語』の里であることと遠野の景色を誇りに思っていたという。
「『遠野物語』の舞台となった場所なんだということは自覚していました。青笹の私の家からは、遠野物語に登場する遠野三山(早池峰山、六角牛山、石上山)がよく見えます。青笹っていうのは、沼のいっぱいある場所なんですが、家から歩いて20分くらいの場所にも沼があったんですね。小さな頃、兄から『あの沼さ仙人いっつじぇ』(あの沼には仙人がいる)と聞かされたんです(笑)。その沼は昼間でも鬱蒼とした木立に囲まれていて、いかにも仙人が住んでいそうだったので、信じていました。近所を歩くだけで、物語の中にいるような感覚でした」
祖母や母から聞いた世間話や噂話は、その土地から沸き立つものとして、リアリティを持って大平さんの記憶の中に刻まれていった。大平さんは、その後18歳で上京し、大学卒業後は川崎市で教員として働いていた。しばらくは仕事に子育てにと忙しく、昔ばなしとは縁遠い生活を送っていたが、15年ほど前、ふと目にした新聞の記事が目に留まった。昔ばなし大学の小澤俊夫先生の講演の記事だ。大平さんは、その記事が気になってしょうがなかった。幼い頃からの記憶を呼び覚まされたのだ。
「理由はわからないんですが、行きたいと思ったんです。その時に、ストーリーテラーの方が語る昔ばなしが強く印象に残りました。それから間もなく、藤井いづみ先生の語りの講座に通い始めました。授業の中で自分でも昔ばなしを語る課題があって、その時に初めて遠野の言葉で『かさこじぞう』を語ったんです。何故遠野の言葉で語ったかは覚えていないんですが、語りと言えば土地の言葉だろうって、あんまり深くは考えていませんでした。そうしましたら、先生から大げさなくらいに褒めていただいて(笑)。それから遠野の言葉で語ることに挑戦し始めたのです」
遠野物語で唯一「津波」を扱った話
2011年に教員の仕事を退職した後、大平さんは遠野と川崎の二つの地域に住み、行き来をしながら語りの活動を行っている。今回、大平さんが選んでくれたのは「妻のたましい」という話。これは、『遠野物語』の99番で、『遠野物語拾遺』と合わせて400話以上ある物語の中で唯一「津波」にまつわる作品である。教員を退職した年に、東日本大震災があった。これは、巡り合わせだと感じた大平さんは、何かできないかとすぐに東北に出向いたが、直後の状況では、とても昔ばなしを聞いてもらえるような状況ではなかった。
「何か私に出来ることをと思ったんですが、4月に行った時点ではまったくそんな状況ではなかったですね。そこで少しですが足湯のボランティアをし、また被災した人たちの話を聞いてまわりました。そして、遠野物語99番を語ろうと思ったんです。2011年の夏頃から語り始め、最初の頃は、私は福二がやっと恋しい妻に会えたのに他の男性といたという、切ない情けない悔しい福二の気持ちで語っていました。でも、何度も語っていくうちに、これは、福二は、この幻想を見る必要があったのではないかと思い始めたんです。つまり恋しい妻ではあるけれども、どこかで気持ちに区切りをつけて自分が前に進まなきゃならない。それを語っているような気がしました。被災地された方たちから、いろんな話を聞いて、そう思うようになりました」

▼大平悦子さんが語る「妻のたましい」を、以下からお聴きいただけます!
Storyteller Hunter vol.02 "Tsuma no Tamashii" by Etsuko Oodaira by Ecocolo_Storyteller on Mixcloud
妻のたましい
むがす。遠野の土淵に福二ず人いでな、この人の兄貴は、北川清ってしぇって土淵の助役をした人だったずす、お爺さんず人は、学者さんで、色々ど本を書えで、村のためにつぐしたような人だったんだど。この福二、歳ごろの若ぇ者になった時、海の近ぐの田の浜ずどごさ、婿に行ったんだど。それがら、わらすにも何人が恵まれで、おだやがに暮らしていだったず。
とごろが、明治二十九年のごどだ、三陸大津波があったべ。福二の家は、海のそばだもんな。ががどわらすど、津波にさらわれですまったんだど。家も流されだず。
福二、ががどわらすに死なれてすまって、われも後をぼっかげで行きてうんたったずども、そうもしてられね。後さ残ったわらすも、ふたりいだったがら、流されだ屋敷跡さ、ぺっこな小屋を建でで、父とわらすふたりど、どうやこうや暮らしていだったんだど。
そうやって、一年ばりたった、夏の初めのころだったず。ある時、福二、夜中に便所さ起ぎだんだど。便所は外便所で、波のしぶきが、足元さかがるような海のそばを、歩いでいがねばねがったず。
その夜は、月ごど明るぐ照っていだったずども、霧のかがった夜だったずもな。福二、そごを歩いていでば、霧の中を、男と女の二人連れが歩いでいだったんだど。福二、ふたりを見て、「はっ」としたず。なんだが、その女子に見おぼえのあるような気してな。
そごで福二、そっこど二人の後をばっかげで行ったず。そうやって、ずぅーと船越村の方までぼっかげでって、だんだんに、だんだんに近づいで、よ-く見でば、間違いね、なんとその女子は、ががだったんだど。一年前に、津波にさらわれて死んだ、福二のががだったんだど。
福二、ががに死なれでがらどいうもの、恋しくて会いたくて、夢にまで出できたががが、今、目の前の、手の届くようなどごさいるわげだ。思わずががの名前を呼ばったず。
その声に、がが、振り返って、福二の方を見て、にこっと笑って、言ったず。「おら、今、この人ど、夫婦になってらもの。」その男は、同じ村の男で、やはり一年前の、津波にさらわれで死んだ男だったず。誰が言ったわげでねぇ、うわさだったずども、その男は、福二が婿に入る前に、まだ娘っこだった福二のががど、互いに思いを寄せあった仲の男だったず。
福二、気持ちおだやがでねじぇな、ががさ、「お前、わらす、めんごぐねのが」って言ってば、がが、その言葉にさっと顔色を変えで、ザメザメーと泣ぇだんだど。そのありさまは、死んだ人が泣ぇでるようでも、死んだ人がそごさいるようでもね、まるで現実の本当のごどのようで、福二、情げなくてせつなくて、がっくりと肩を落として足元さ目落どしたんだと。
その間に、男と女子のふたり連れ、足早にそこを去って、ずぅーと小浦ずどごさ行ぐ方の山かげさ入って、めんなぐなったず。福二、あわででふたりをばっかげだずもな。ほだども、なんぼが行ったどごで、ハッと「あぁー、あのふたりは、死んだものだー」って、気づいで、ぼっかげるのをやめだんだど。
それから、福二、すぐにはそごを動ぐ気になれなくて、ふたりがいなくなった方をながめながら、色々と考えごとをして、ずぅーとそごさ立っていだったんだど。そして、夜が白々と明げできてがら、やっと家さ帰ぇったず。
その後、福二、具合が悪ぐなって、しばらーぐ病んだんだどさ。
![]()
おおだいら・えつこ/東京と遠野で語り部として活動している。川崎市日本民家園で偶数月の第三土曜日に遠野の語りを行っている。
かみじょう・けいこ/編集者・ライター。アート、デザイン、カルチャーの分野で雑誌、書籍編集を行う。昔ばなし大学の受講生でもある。